2025年春、突如としてTikTokを席巻した謎のフレーズ「エッホエッホ」
人気アイドルグループFRUITS ZIPPERの松本かれんさんをはじめ、多くのユーザーが「えっほえっほ」と小走りするような仕草と共に、様々な豆知識を披露する動画が大流行中です。
「”エッホエッホ”って、一体どういう意味で使われているの?」
「そもそも、あのフレーズと動きの元ネタは何?」
「なぜこんなに一気に広まったんだろう?」
「批判的な意見もあるって本当?」
この記事では、そんな「エッホエッホ豆知識」の意味や基本的な使い方、元ネタ、SNSで拡散していった経緯について紹介していきます。
TikTokで話題沸騰中の謎フレーズ「エッホエッホ」とは?
まずは、この奇妙で耳に残るフレーズ「エッホエッホ」の基本的な意味と、TikTokでどのように使われているのかを見ていきましょう。
「エッホエッホ」の基本的な意味と使い方
「エッホエッホ」というフレーズ自体に、特定の深い意味はありません。
元ネタとなった写真のイメージから「何かを一生懸命伝えようと走っている様子」を「エッホエッホ」と擬音化したのが始まりです。
定番の使い方:「エッホエッホ、〇〇って伝えなきゃ」構文
TikTokやSNSで「エッホエッホ」が使われる際の、最も定番の形がこの構文です。
「エッホエッホ、〇〇(伝えたい豆知識や情報)って伝えなきゃ、エッホエッホ」
この「〇〇」の部分に
- 知っているとちょっと賢くなれる(かもしれない)豆知識
- 思わず「へぇ!」と言ってしまう面白い情報
- 個人的なニュースや発見
などを入れて、リズミカルな音楽に乗りながら、小走りのようなジェスチャーと共に披露するのがお決まりの動画フォーマットです。
- 言葉自体に深い意味はない
- 「何かを一生懸命、急いで伝えたい様子」を表現
- 「エッホエッホ、〇〇って伝えなきゃ」の構文が基本
- 小走りのようなジェスチャーとセットで使われることが多い
具体的な使用例
実際に、TikTokではどんな情報が「エッホエッホ」と共に語られているのでしょうか?
- 一般的な豆知識系:
- 「エッホエッホ、ブロッコリーのつぶつぶって、花のつぼみなんだって伝えなきゃ、エッホエッホ」
- 「エッホエッホ、キリンの睡眠時間って、すごく短い(1日に20分程度)って伝えなきゃ、エッホエッホ」
- ちょっと意外な事実系:
- 「エッホエッホ、パンダの尻尾の色は本当は白いって伝えなきゃ、エッホエッホ」
- 個人的な出来事・心の声系:
- 「エッホエッホ、今日締め切りのレポートがあるって伝えなきゃ(自分に言い聞かせ中)、エッホエッホ」
- 「エッホエッホ、大好きな推しの新しいグッズが発売されたって、みんなに伝えなきゃ、エッホエッホ」
このように、共有したい情報なら何でも当てはめられる汎用性の高さが、「エッホエッホ」が多くの人に使われ、流行を加速させた大きな理由の一つと言えるでしょう。
「エッホエッホ」の元ネタはメンフクロウのヒナの写真
「エッホエッホ」ミームの全ての始まりは、オランダの写真家ハニー・ヘーレ氏が撮影した、地面を走っているように見えるメンフクロウのヒナの写真です。
短い足で一歩を踏み出し、翼を少し広げたその姿が、まるで「何かを伝えるために、短い足で一生懸命走っている」ように見えたことから、インターネット上で「可愛い!」「面白い!」と話題になりました。
写真のインパクトと、「何かを伝えたい」という想像が組み合わさり、X(旧Twitter)で「エッホエッホ、〇〇(伝えたいこと)って伝えなきゃ」という独特のフレーズが自然発生的に生まれました。
写真のインパクトと、このキャッチーなフレーズが絶妙にマッチし、多くのユーザーの心を掴んで拡散していったのです。
メンフクロウってどんな鳥??
顔がハート型の白い仮面をつけたように見えるのが特徴的なフクロウの一種。世界中の温帯・熱帯地域に広く分布しており、日本でも飼育されていることがあります。
なぜここまで流行った?「エッホエッホ」ミーム化への道のり
一枚の写真とフレーズが、どのようにしてTikTokを席巻するほどの巨大なトレンド(=ミーム)へと成長したのでしょうか。その拡散のプロセスをステップごとに見ていきましょう。
Step1: X(旧Twitter)での大喜利が拡散のきっかけ
「エッホエッホ」ブームの火付け役となったのは、X(旧Twitter)。
ユーザーたちは、あのメンフクロウのヒナの写真に「エッホエッホ、〇〇って伝えなきゃ」のフレーズを添えて、大喜利のように様々な「伝えたいこと」を投稿し始めました。
「面白い!」「その発想はなかったw」「わかる!」といった共感を呼び、リポストや「いいね」を通じて、このフレーズと写真の組み合わせはじわじわと認知度を高めていきました。
Step2: TikTokで「エッホエッホのうた」が大ヒット!
Xでの盛り上がりを受け、次に大きな波が来たのがTikTokです。ここで決定的な役割を果たしたのが、「エッホエッホのうた」の登場でした。
ミュージシャンのうじたまい氏などが制作したとされる、一度聴いたら耳から離れないキャッチーな楽曲が、「エッホエッホ」のリズム感とフレーズに完璧にマッチ。
このオリジナル音源を使った動画投稿がTikTok内で急増し、一気にバイラルヒットとなっています。
Step3: 真似しやすい動画フォーマットの確立
「エッホエッホのうた」のヒットと同時に、TikTokでは「音源に合わせて小走りジェスチャーをしながら豆知識を披露する」という、非常に真似しやすい動画フォーマットが確立。
FRUITS ZIPPERの松本かれんさんのような人気インフルエンサーやアイドルが取り上げたことも、流行をさらに後押しする大きな要因となりました。
流行の経緯まとめ
| 流行ステップ | プラットフォーム | 主な出来事・現象 |
|---|---|---|
| 起源 | 写真 | ハニー・ヘーレ氏によるメンフクロウのヒナの写真が話題に |
| フレーズ誕生 | X (旧Twitter) | 写真から着想を得て「エッホエッホ、〇〇って伝えなきゃ」構文が誕生 |
| 初期拡散 | X (旧Twitter) | 大喜利形式の投稿が広まり、認知度が徐々に向上 |
| ブレイク | TikTok | 「エッホエッホのうた」が登場し、音源利用動画が急増 |
| フォーマット確立 | TikTok | 音源+小走りジェスチャー+豆知識披露の動画フォーマットが定着 |
| 大流行 | 各SNS | アイドルやインフルエンサーも参加し、社会現象レベルに拡散 |
SNSプラットフォーム別:「エッホエッホ」の使われ方と反応
同じ「エッホエッホ」ミームでも、TikTokとX(旧Twitter)やでは、その使われ方やユーザーの反応に少し違いが見られます。
TikTok:音源とチャレンジ動画が中心
TikTokでは、「エッホエッホのうた」の音源を使った動画が主流です。
「#エッホエッホ豆知識」「#エッホエッホチャレンジ」といったハッシュタグが付けられ、ユーザーは新しい豆知識動画を投稿しています。
「音源 × 真似しやすいフォーマット」というTikTok特有の拡散力が最大限に発揮され、特に若年層を中心に、一種の「お祭り」のような状態で楽しまれています。
X(旧Twitter):大喜利から日常投稿まで多様化
X(旧Twitter)では、流行のきっかけとなった大喜利的な使い方も根強く残っています。
面白い一言や時事ネタを「エッホエッホ」構文に当てはめて投稿するユーザーが多く見られます。
また、単に「急いでる!」「伝えたいことがある!」といった日常の出来事や感情を表現するために、このフレーズが使われることもあります。
TikTokトレンドへのX(旧Twitter)民の反応
Xで生まれたネタがTikTokに持ち込まれ、より大衆的でキャッチーな形に変容して大流行することに対し、「元々の面白さが失われた」「安易な消費だ」と感じる人もいるようです。
X(旧Twitter)をメインに利用しているユーザーの一部には、TikTokで流行するコンテンツに対する潜在的な反発感が原因とみられます。
「エッホエッホ」も、元々Xで楽しまれていた側面があるため、一部でSNS間の対立構造が生まれてしまっています。
まとめ
この記事では、2025年春にTikTokを中心に大流行した「エッホエッホ」について、その意味、使い方、元ネタ、流行の経緯、そして一部で見られる批判の声まで、詳しく解説してきました。
- 意味: 「一生懸命伝えたい様子」を表す擬音語・擬態語。
- 元ネタ: オランダで撮影されたメンフクロウのヒナの写真。
- 構文: 「エッホエッホ、〇〇って伝えなきゃ」が基本形。
- 流行の経緯: Xでの大喜利 → TikTokでの楽曲ヒット&フォーマット確立。
- 特徴: 真似しやすい、汎用性が高い、音源がキャッチー。
- 批判の背景: TikTokへの反発、流行サイクルの速さ、価値観のギャップなど。
「エッホエッホ」は、一枚のユニークな写真が、SNSを通じて言葉遊びとなり、さらに音楽と動画フォーマットを得て爆発的に拡散するという、SNS間をまたいだ現代ならではのネットミーム現象です。
今後も「どのような形でネットミームが誕生するのか」楽しみにしていきましょう。


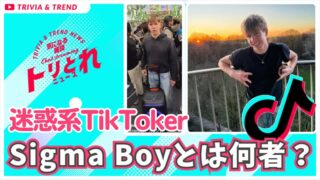
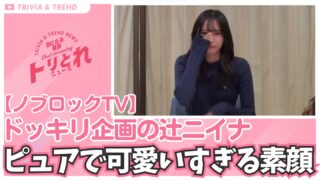

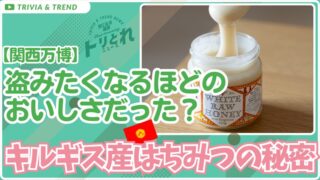
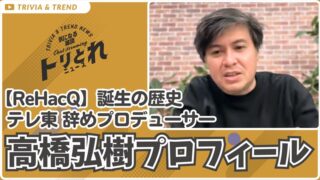


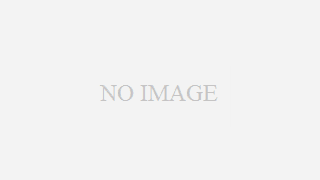


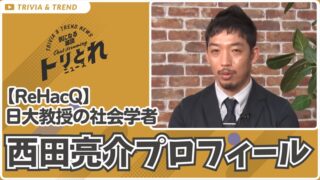



コメント