「大学いも」の【大学】ってどういう意味があるんだろう?
屋台やテレビ、回転ずしなどで見かけることも多い「大学いも」。
でもその名前を聞いて、
「えっ、なんで“大学”?」「大学生と関係あるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は「大学いも」という名前の由来には、いくつかの説があるんです。
そして、意外なことに“これが正解!”というハッキリした理由は、まだ分かっていません。
この記事では、そんな「大学いも」の名前にまつわる有力な説や、知られざるルーツなど、知るとちょっと誰かに話したくなる豆知識を分かりやすくご紹介します!
「大学いも」の由来3つの有力説
大学いもの名前の由来として語られる説はいくつかありますが、特に有力とされているのは以下の3つです。
どれも「大学」や「大学生」がキーワードになっています。
諸説1:大学生に大人気!学生街のソウルフード説
最も多くの人に支持されているのが、「大学生の間で人気だったから」という説です。
- 時代背景:大正時代から昭和初期にかけて
- 場所:学生が多く集まる「学生街」(大学や専門学校などが集まっている地域のこと)
- 理由:
- 安くてボリュームがあり、お腹を満たせる
- 甘くて美味しい
- 特に、東京大学の赤門前にあった「三河屋」というお店で売られていた、揚げたさつまいもに蜜をかけたものが東大生に大人気だったという話が有名です(1940年頃まで)。
当時の大学生は、苦学生も多く、手軽に空腹を満たせるさつまいもは貴重な存在でした。
そのため、学生たちにとって大学いもは特別な食べ物だったのかもしれませんね。
諸説2:苦学生の学費稼ぎのための発明説
次に有力なのが、「大学生が学費を稼ぐために作って売っていたから」という説です。
- 時代背景:昭和初期(世界恐慌などの影響で不景気な時代)
- 背景:学費を払うのに苦労する学生が多かった
- エピソード:
- ある東京大学の学生が、学費を稼ぐために昭和2年頃に大学いもを考案し、売り始めたという話があります(浅草の大学いも店「千葉屋」関係者の話より)。
- さつまいもと砂糖という安価な材料で簡単に作れるため、学費稼ぎの手段として理にかなっていた。
この説も、当時の厳しい社会状況を考えると十分にあり得る話ですね。
学生の生活の知恵から生まれたのかもしれません。
諸説3:当時のトレンド?「大学」ネーミング流行説
そしてもう一つ、「商品名に“大学”と付けるのが当時流行していたから」という説もあります。
- 時代背景:明治から大正時代
- 背景:ハイカラなイメージや権威の象徴として「大学」という言葉が好まれた
- 具体例:
- 「大学ノート」:現在も使われているこの名称も、この時代の流行に乗って名付けられたと言われています。
この流行にあやかって、大学いもも「大学」という名前が付けられた可能性も考えられます。
| 説 | 内容 | 時代背景 | 関連エピソードなど |
|---|---|---|---|
| 大学生に人気説 | 大学生の間で人気だったから | 大正~昭和初期 | 東大赤門前の「三河屋」 |
| 学費稼ぎ説 | 大学生が学費稼ぎのために売っていたから | 昭和初期(不況) | 東大生が考案したという話(千葉屋) |
| ネーミング流行説 | 商品名に「大学」と付けるのが流行っていたから | 明治~大正時代 | 「大学ノート」など |
結局のところ、どの説が正しいのかはっきりしていませんが、いずれにしても「大学」や「大学生」と深い関わりがあったことは間違いなさそうです。
大学いものルーツは中国にあり!意外な起源とは?
実は、大学いもの調理法そのものは日本オリジナルではなく、中国料理にルーツがあると言われています。
中華料理「バースーバイシュー」が原型

大学いもの原型とされるのは、中国の「抜絲白薯(バースーバイシュー)」や「蜜餞紅芋(ミーチェンホンユイ)」と呼ばれる料理です。
これらは、揚げたさつまいもに飴状の蜜をたっぷりと絡めたもので、見た目も大学いもによく似ています。
この中国の伝統的なさつまいもスイーツが、日本でアレンジされて「大学いも」として広まったと考えられています。
日本と中国の大学いも、ここが違う!
中国版と日本の大学いも、似ているようで実はいくつか違いがあります。
- 黒ゴマの有無
日本の大学いもには仕上げに黒ゴマをかけるのが一般的ですが、中国の原型とされる料理には基本的に黒ゴマは使いません。 - 蜜の固さと味付け:
- 中国版:蜜が冷えるとパリパリに固まり、糸を引くような状態になるのが特徴。味付けもシンプルな甘さのものが多いです。
- 日本版:蜜が比較的柔らかく、しっとりとした食感のものが多い。醤油を少し加えて甘じょっぱくしたり、みりんを加えたりと、味付けにもバリエーションがあります。
日本の大学いもは、日本人の好みに合わせて独自に進化したものと言えそうですね。
まだまだある!大学いもの面白い豆知識
大学いもには、名前の由来やルーツ以外にも、人に言いたくなる面白い豆知識があります。
地域ごとの呼び名と形のバリエーション
大学いもは、実は地域によって呼び名や一般的な形が少し異なることがあります。
- 呼び名の違い:
- 関西地方:一部で「中華ポテト」と呼ばれることがあります。これは、関西の中華料理店に中国出身の料理人が多く、その影響で中国料理としての認識が残っているためと考えられています。
- 形状の違い:
- 関東:丸型、大きめの乱切り、輪切りなど、比較的ゴロッとした形状が一般的。
- 関西:スティック状(細切り)のものもよく見られます。
引っ越しや旅行などで違う地域に行った際に、大学いもの違いに注目してみるのも面白いかもしれませんね。
まとめ
今回は、大学いもの名前の由来から、そのルーツ・豆知識まで幅広くご紹介しました。
- 名前の由来:大学生に人気だった説、大学生が学費稼ぎに売った説、当時のネーミング流行説など諸説あるが、いずれも「大学生」が深く関わっている。
- 起源:中国料理の「抜絲白薯(バースーバイシュー)」などがルーツとされ、日本で独自に進化した。
- 豆知識:地域による呼び名・形状の違いもある。
結局、大学いもの名前の本当の理由は謎のまま。
でも、100年近くもみんなに愛されてきた背景には、きっと学生たちの青春や、時代の空気が詰まっているんでしょうね。
次に大学いもを食べる時、こんな話をちょっと思い出してみてください。
いつもより、もっと美味しく感じるかもしれませんよ!

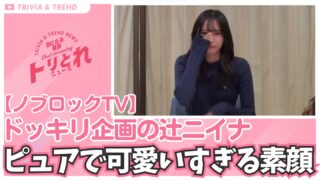


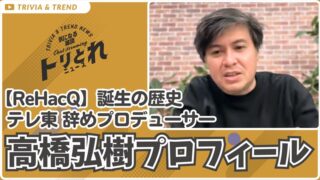
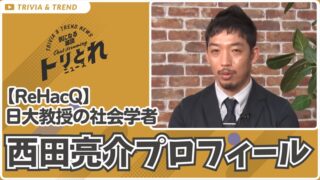
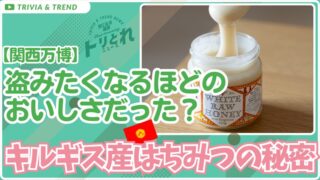



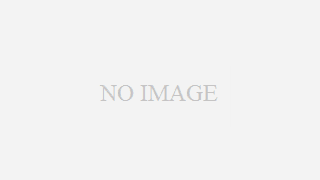
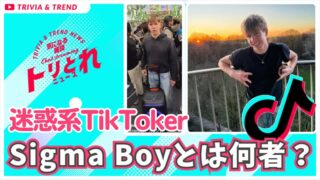

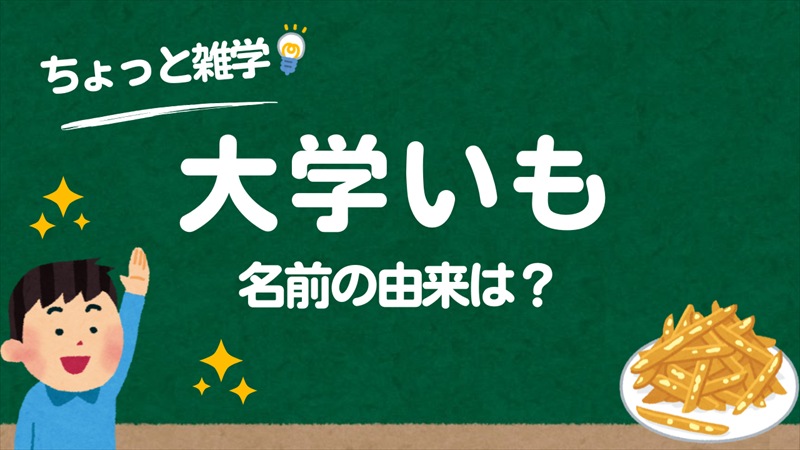


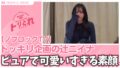
コメント